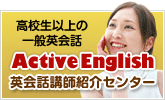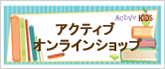(お花見行きたいです!)
こんにちは!アクティブ石田です。
いよいよ4月から始まる、新学習指導要領の改訂に伴う英語についてここでおさらいをしてみたいと思います。
まずは、そもそもの話、なんで指導要領に今回大きな改訂が入るのか・・・ということです。
前回、このように大きな改訂が入ったのは「脱ゆとり」を掲げた2011年の新学習要領です。
ゆとり教育の弊害を反省し、もう一回学習量増大に舵取りを行ってから約10年。
その間に、グローバル化やAIの普及などがあり、より「コミュニケーション力」や「情報収集能力・情報活用能力」が必要になってきました。
こうした現代の特性に合わせて教育も変わっていかなければならない、ということで、前回の改革が「脱ゆとり」であるのであれば、今回の改革はコミュニケ―ションや情報活用に重きを置いた「生きる力」を養う教育と言えるのかもしれません。
もともと、「俺が俺が」と目立つ行動を好まない国民性と言われる日本人は、個を主張する教育ができていないために、グローバル社会ではどうしても不利に働きがちなんですよね。
ここが改善できるのかどうか、難しいところです。
それはともかくとして、今回は具体的にどのように教科書や指導が変わっていくのかについて、早速おさらいをしていきましょう。
まずは、教科書の改訂スケジュールとそのポイントについてです。
【2020年4月~】
小学校で、全面的に新学習要領に沿った教科書に切り替わります。
小3・小4では「外国語活動」が週に1回始まります。
成績は、つきません。
教科書は既に今年度も使っている「Let’s Try!」を継続して利用します。
小5・小6では、外国語が1教科として加えられます。
週に2回の授業が行われ、成績もつきます。
教科書会社は7社参入し、市町村ごとに7種のなかから1つを採択して使用します。
【2021年4月~】
中学校で、新学習要領に沿った新しい教科書が全面実施されます。
小学校よりも1年遅い切り替えになります。
コミュニケーション力を養う言語活動を実施している小学校の外国語活動ですが、「中学校でもそういった展開の仕方を引継ぎ、意味のある文脈の中でのコミュニケーションを通して繰り返し活用し定着を図ることが出来るように」学んでいきます。
※カッコ内は平成29年改訂中学校学習指導要領解説(外国語編)から引用
小学校・中学校共に、英語の授業で注目されており重視される項目は、ずばり!
「言語活動の充実」
です。
え??言語活動って何?!と聞きたくなってしまいますよね~。
そんな言葉、あったっけ?
ここで言う言語活動、つまりは「会話」「対話」だと思っていれば大体間違ってはいないです。
英語学習においては、近年「4技能の重視」、とか言葉も見聞きされていらっしゃると思いますが、この4技能、つまり「話す」「聞く」「書く」「読む」も、本来どれも言語活動のひとつ、ということになります。
ですが、小学校(+中学校も)でいう言語活動の充実、と言えば、上記4つのうち「書く」「読む」よりは、「話す」「聞く」をより重要視して授業が進んでいくことが想定されています。
では次に、小学校の英語教科書がどうなっているのか、一例を挙げます。
1ユニットが8ページ構成になっていて、
1・2ページ目 テーマ・会話文を掲載
3・4ページ目 短い会話文
5・6ページ目 英語でのやりとり
7・8ページ目 発表しよう
という構成で、なんと英文法の解説はありません。
文法の間違いをどうこう指摘して子供が委縮してしまわないように、という配慮なのかもしれませんが、まずは言語活動(とにかく話してみる、対話してみる)をさせておいて、最後にさらーっと文法項目に触れる、という構成については、今後、塾などでも増えていく、主流の英語指導の流れになっていくかもしれません。
間違いを恐れずに発言しよう!通じればいいんだから、英文法解説はやり過ぎないで!!
というこのスタンス自体は、私も大賛成です。
ですが、自分が小学校5、6年生だったころの思考や学習に対する取り組みを思い出すとして・・・・・。
うん、やっぱり、きちんと英語の文の仕組みを知ってから応用していきたいと思うだろうな・・・とも感じるのです。
もちろん、人によって色々違うとは思うのですが、文法をよく知らなければ「間違っても平気」で良く知ってしまうと「間違うのが怖くて発言できない」っていうのは、どうも何かが違っているような気がしてなりません。
話はすごーく飛んでしまうようなのですが、私がSNSをフォローしている、とある日本人女性でNYで起業して活躍されている方がいらっしゃいます。
彼女が最近アップしていた記事で、「英語上達のコツ」というものがあり、それによると、一番のポイントは、
・完璧を目指さなくてよい
ということで、これは「間違いを恐れずに話そう」という内容とイコールだと思うのです。
ですが、もう一つのポイントとしては、
・日本語なまりはあってもOKだけど、語彙と文法を頑張る
とありました。
つまり、お国訛りはあるけれど、難易度高めの英単語やきちんとした英文法で話すことによって「教養のある人。頑張って英語を身につけた人」ということで世界のビジネスシーンでも一目置かれる存在になれるそうです。
逆に言うと「Oh my god!」「Really??(Rの巻き舌強め)」のような、「それっぽい」発音で、大げさなリアクションだけをしているような英語は、たしかに「それっぽく」聞こえるかもしれないですが、国際ビジネスの場では評価されない、ということになるのではないかと思います。
もちろん、文法偏重の日本の英語教育をことさらに擁護する気はないのですが、やっぱりきちんと英文法も押さえてほしいなあ、とは感じる私なのです。
2020年からの新学習指導要領について、成功だったのか、失敗だったのか、結果はまだ当分先まで分かりませんが、個人的には、もう少し英会話だけでなく、英文法についても、きちんと学習するようなテキストになっていってほしいなあ、と思っています。
2020.03.12 | 2041 | 代表メッセージ